アルゴスの利用分野
 |
|
||
 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
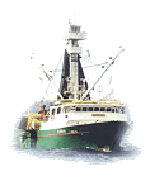 |
||
アルゴスシステムは、海洋・気象観測や野生動物の研究など、さまざまな目的で世界中の科学者・研究者に利用されています。いろいろな利用分野や、日本の研究者による利用例などを紹介します。
トライトンブイ
トライトンブイは、エルニーニョ現象などを観測するための定置ブイで、JAMSTEC(海洋研究開発機構)によって、西太平洋の赤道域を中心に展開されています。海上の風向、風速、気温、湿度などの気象や、海中の水温、塩分濃度などを観測しています。観測データは、アルゴスシステムによって収集・配信されています。
⇒ JAMSTECのトライトンブイのページ
アルゴ計画
『アルゴ計画』は、世界中の海に合計3000本のフロートを展開し、海洋データを継続的に収集・蓄積するための国際的なプロジェクトです。アルゴフロートは、水深2,000mの海中で漂い、10日ごとに海面に浮上します。浮上時に、各深度での水温・塩分の値を観測し、海面でこれらのデータをアルゴスの衛星に送信した後、再び自動的に潜水します。
⇒ アルゴ計画ホームページ
火山の観測
アルゴスシステムは海ばかりではなく、陸上でも用いられます。砂漠や山岳地帯での観測では、衛星が唯一の通信手段です。日本でも、三宅島や霧島などの火山の観測に、アルゴスシステムが用いられています。
海洋動物の生態調査
アザラシ、ウミガメ、イルカ、ペンギンなどさまざまな海洋動物の生態調査にアルゴスシステムが用いられています。アルゴスシステムの位置算出機能によって動物の移動経路を追跡できるほか、潜水パターンや環境温度などを観測します。
⇒ 日本ウミガメ協議会によるウミガメ衛星追跡
渡り鳥の追跡
ツルやハクチョウ、アホウドリなど、たくさんの種類の鳥調査にもアルゴスシステムが用いられています。アルゴスの衛星装置は極めて高感度で、携帯電話よりも微弱な電波ですら受信可能です。小さいものでは、20g以下のアルゴス送信機も利用されています。
⇒ 渡り経路の衛星追跡調査
(公益財団法人 日本野鳥の会)
陸上動物
ニホンザルやツキノワグマといった陸上の動物の生態調査にも利用されています。移動範囲が狭く、精度の高い位置データが必要な場合には、GPS位置を送信するアルゴス送信機も利用できます。
漁業資源の保護
アルゴスは環境調査のためだけでなく、環境の保護の目的でも利用されています。漁業資源保護の目的で、漁船の操業管理に多くのアルゴス送信機が用いられています。
